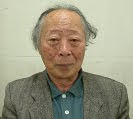顧問 中村美智子
家族探す涙の頬に降りかかる氷雨は
被災の地を凍み閉じこめる
三食を食い安閑と眠るわがせめて
募金の額を惜しまじ
泰山木の大輪の花天に咲けり
「原発NO」の署名にわれも背を立つ
枇杷も胡桃も鈴なり実るわが団地
「原発NO」の署名に歩く
放射能は人を選ばずと言うときに
拒みいし人も署名に傾く
原爆を断つと生ききし六十五年
この一途さをひそかに恃む
シクラメンの花は寒気をひきしめて
咲き冴ゆるなり新しき年
2011年12月24日土曜日
脱原発の社会をめざして
府中革新懇 事務局長 田部 章
3月11日の夜から、巨大津波に呑みこまれていく東北の人と町、原発の爆発と放射能から逃れる福島の人々の映像。祖母の形見となったトランペットを吹き号泣した女子高生や外で遊べない福島の子どもたち、故郷を追われて転々移動する人たち。復旧復興や安全を言う政府や学者への不信が積み重なる。「国難」のときTPPに参加するとは・・・放射能測定や除染の要求に応えようとしないしない自治体の姿勢に怒りの声が出る。脱原発の社会をめざして具体的要求で攻めていく。「東日本大震災;恐ろしくて 哀しくて 声をあげて泣いて 生きていこう」
3月11日の夜から、巨大津波に呑みこまれていく東北の人と町、原発の爆発と放射能から逃れる福島の人々の映像。祖母の形見となったトランペットを吹き号泣した女子高生や外で遊べない福島の子どもたち、故郷を追われて転々移動する人たち。復旧復興や安全を言う政府や学者への不信が積み重なる。「国難」のときTPPに参加するとは・・・放射能測定や除染の要求に応えようとしないしない自治体の姿勢に怒りの声が出る。脱原発の社会をめざして具体的要求で攻めていく。「東日本大震災;恐ろしくて 哀しくて 声をあげて泣いて 生きていこう」
息子一家が被災 本気で世直しを!
世話人 武藤幸子
12年前、息子が浪江に転勤した時から、ずっと心に引っかかっていた「原発事故」が3月12日現実のものになってしまった。ようやく連絡が取れた息子一家に「とにかく早く遠くに逃げなさい」と。避難所を転々とし、ガソリンがようやく手に入り八王子のわが家に。しかし、中三の孫は、「福島が大好き、友達と一緒にいたい」と転校した学校には、2日しか行けずに、1ヶ月後には福島に。放射能の影響を心配して呼びよせた私は、被災した孫たちの思いを推し量ることができずに悩んだ。子どもたちへどのような影響を及ぼすのかとても心配。9月にお墓参りに故郷福島に。たわわに実った黄金色の稲、色鮮やかに咲いたコスモス、いつもと変わらない様に悲しみと怒りが。世の中を、社会を少しでも変えたいと私なりに歩んできたが、力不足を実感。今多くの人が何かをしなければと行動を始めている。原発を安全と嘯いてきた為政者を包囲して本気で世直しをしよう。
12年前、息子が浪江に転勤した時から、ずっと心に引っかかっていた「原発事故」が3月12日現実のものになってしまった。ようやく連絡が取れた息子一家に「とにかく早く遠くに逃げなさい」と。避難所を転々とし、ガソリンがようやく手に入り八王子のわが家に。しかし、中三の孫は、「福島が大好き、友達と一緒にいたい」と転校した学校には、2日しか行けずに、1ヶ月後には福島に。放射能の影響を心配して呼びよせた私は、被災した孫たちの思いを推し量ることができずに悩んだ。子どもたちへどのような影響を及ぼすのかとても心配。9月にお墓参りに故郷福島に。たわわに実った黄金色の稲、色鮮やかに咲いたコスモス、いつもと変わらない様に悲しみと怒りが。世の中を、社会を少しでも変えたいと私なりに歩んできたが、力不足を実感。今多くの人が何かをしなければと行動を始めている。原発を安全と嘯いてきた為政者を包囲して本気で世直しをしよう。
2011年12月20日火曜日
引間博愛さんを偲ぶ 労働運動の右翼的再編に体を張って挑む 中村美智子(元新日本婦人の会都本部会長、東京革新懇顧問)
引間博愛さんの突然の訃報(一二月三日)に息をのんだ。「しんぶん赤旗」に掲載された経歴は十七行・百七十字・異例に長い。私はその一字一行に見入り紙面を閉じることができなかった。
この十七行にこめられた引間さんの経歴は、戦後日本の労働運動の縮図のように私の胸に重く響いた。
襲いくる反共攻撃幾たびぞ挫折なけれは確信の湧く(歌集「秩父讃歌」より)
日本の労働運動の右翼的再編の渦に抗い、体を張って挑み、時代に叶った組織づくりの最前線に立たれた。年金者組合の産みの親でもある。
私もいろいろな場面で御一緒し写真まで横並びしたのがある。しかし、その引間さんが歌人であることを知ったのは、一九九十年代後半、私が「新日本歌人」に入会してからのこと。もっと驚いたのは「私の戸籍は秩父でね」である。東京革新懇の会議で隣席の時は、秩父の誰れそれのこと、秩父事件のことで話が弾んだ。
生まれしは北海道にて本籍は秩父なりけりいづれも誇る(歌集「秩父讃歌」より)
生活要求と世直し・自由・自治を柱に闘った父祖の血脈と自分の生き様を重ね「誇る」と詠われた引間さん。たけだけしいもの言いをしない、いつも「沈着で温和」な引間さん。私の隣席に座られることはもうない。
困民党の蜂起の歴史相共に継ぎきし君といま別れゆく 合掌
(経歴)
12月3日、心不全のため逝去。享年91歳。
1920年3月、北海道夕張市生まれ。1946年、神田運送で労組結成、支部書記長になる。1950年11月、レッドパージで神田運送を解雇されるが、52年6月に撤回される。1954年10月、全国自動車運輸労働組合委員長に就任、その後、全日本運輸一般労働組合委員長、統一労組懇常任代表委員として労働組合運動の階級的民主的強化、全労連の結成に尽力。1989年9月、全日本年金者組合を創立し、初代委員長。全労連顧問、全国革新懇代表世話人などを歴任。東京革新懇の結成(1981年2月3日)よびかけ人32氏の一人で、代表世話人を長く務め、2010年から顧問。
新日本歌人協会会員。歌集『明日の陽』『秩父讃歌』など
2011年11月15日火曜日
町長先頭に新しいまちづくりを始めた伊豆大島で政治革新のロマンを語る ”観光の町づくり 島づくり” 川島理史大島町長が挨拶 東京革新懇宿泊学習交流会
東京革新懇は11月5、6日日、「新しい町づくりを始めた伊豆大島で政治革新のロマンを語ろう」と宿泊交流集会を開催しました。
観光のまちづくりについて、湯河原革新懇の高山正義事務局長が記念講演。
「まちづくりには、保守も革新もない」との考えで、湯河原駅前の「明店街」活性化対策草案を発表し、いろいろな方に届けたら大きな反響を呼び、町議会議長や副議長、さらに老舗の旅館社長でもある湯河原温泉まちづくり協議会会長と懇談することができたこと、東日本大震災直後に、町長に、「湯河原町のホテル・旅館・民宿を避難先として利用できるように特別措置を」などの申し入れを行ったこと、また、町の後援を得て「地震津波勉強会」を行ったら173人の参加があり大きく成功させることができたと、話しました。(上写真は高山湯河原革新懇事務局長)
川島理史大島町長が挨拶し、「町民が主役」の島づくりに向けて粘り強く取り組んでいることを力強く述べました。また、「町民の会」の磯山仲雄会長は、川島町長誕生のドラマと継続・発展させる決意を語り、参加者に感動を与えました。(左は川島町長)
(川島理史大島町長と参加者。岡田港で)
観光のまちづくりについて、湯河原革新懇の高山正義事務局長が記念講演。
「まちづくりには、保守も革新もない」との考えで、湯河原駅前の「明店街」活性化対策草案を発表し、いろいろな方に届けたら大きな反響を呼び、町議会議長や副議長、さらに老舗の旅館社長でもある湯河原温泉まちづくり協議会会長と懇談することができたこと、東日本大震災直後に、町長に、「湯河原町のホテル・旅館・民宿を避難先として利用できるように特別措置を」などの申し入れを行ったこと、また、町の後援を得て「地震津波勉強会」を行ったら173人の参加があり大きく成功させることができたと、話しました。(上写真は高山湯河原革新懇事務局長)
川島理史大島町長が挨拶し、「町民が主役」の島づくりに向けて粘り強く取り組んでいることを力強く述べました。また、「町民の会」の磯山仲雄会長は、川島町長誕生のドラマと継続・発展させる決意を語り、参加者に感動を与えました。(左は川島町長)
(川島理史大島町長と参加者。岡田港で)
2011年11月9日水曜日
子どもから虐待を守るために ―児童虐待の背景にある貧困―
「貧困と格差のない社会をめざして」④
弁護士
平湯 真人
(子ども虐待防止センター理事長、「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク共同代表)
都教組、東京地評などが参加する「子どもを貧困と格差から守る連絡会議」は9月15日に、子どもの虐待防止に取り組んでいる平湯真人弁護士を講師に招き、学習会を行いました。その内容を紹介します。
○誰を罰するかよりも
虐待は特殊な親や家庭の問題ではありません。虐待事件は誰を罰するかよりも、そもそもの防止が大事で、この立場で子ども虐待防止センターの活動を行っています。
児童相談所に情報が寄せられても、民法の親権条項で取り組みが制約されてきました。最近、民法の改正があり、児童虐待を防ぐため親権の一時停止ができるようになりましたが、親の懲戒権は制限付きで残りました。
○児童虐待をめぐる状況
平成12年に児童虐待防止法ができ、児童相談所への市民からの通告が奨励され、立ち入り調査が認められるようになりました。子どもを虐待から守る官民の取り組みの中で、通告件数は急増し年間5万余にのぼり、児童虐待による死亡は49人(47事例)と報告(平成21年度)されています。そのうちゼロ歳児が20人(40.8%)と一番多く、0~5歳児が約9割(43人)を占めています。
○虐待の背景は
貧困など社会的環境の背景についての把握が弱かったのではないでしょうか。ゼロ歳児が多いということは、生まれた時から拒否されていたと言えます。虐待が行われた家庭の状況(資料)を見ると、経済的貧困と孤立が大きな要因として絡んでいることが明らかです。虐待を防止するためには、貧困と社会的孤立を重視する必要があります。
○背景と虐待行為を繋ぐもの
しかし、経済的背景があったとしても、なぜ虐待行動をやってしまうのか、その理由はわかりにくいのが実態です。昔、家庭は生産・消費の場で、働かないことに対する体罰がありました。家庭の役割が変化しましたが、今は裕福でも将来の貧困不安を解消するために、子どもの高学歴をのぞみ、勉強を強要するケースも増えています。しつけが動機であったとしても、子どもが言うことを聞かないからと、親の支配欲求と絡んで体罰がエスカレートする傾向があります。
○学校と地域の役割~監視でなく家庭支援を
都の児童相談所のほかに、区市町村などの自治体で、子ども家庭支援センターが設置されています。地域では、虐待の怪我を探すような監視ではなく、困っている家庭の支援が求められています。
そして、「学校に福祉の発想を」の期待が高まっています。「個人情報の保護」があるから、家庭のことに口を出してはいけない、との誤解が若い先生を中心に広まっています。これでは学校の役割が先細ってしまします。今度の震災で、父子家庭だった子どもが津波で父親を亡くし、校長が、離婚した母親を探し出し、ようやく子どもと繋げることができたケースを聞きました。
先生の研修会の参加が少ないのが残念です。都教委「虐待防止のパンフレット」を作成しましたが、できれば時間をかけて研修してほしい。何よりも大事なことは、知識よりも感性の問題、顔を腫らした子どもに何が起きているか推察できる「感性」を先生に磨いてもらいたいと、願っています。
虐待が行われた家庭の状況
家庭の状況 合わせて見られる他の状況上位3つ
状況 件数 割合(%) ① ② ③
ひとり親家庭 460 31.8 経済的困難 孤立 就労の不安定
経済的困難 446 30.8 ひとり親家庭 孤立 就労の不安定
孤 立 341 23.6 経済的困難 ひとり親家庭 就労の不安定
夫婦間不和 295 20.4 経済的困難 孤立 育児疲れ
育児疲れ 261 18.0 経済的困難 ひとり親家庭 孤立
(文責;編集部)
弁護士
平湯 真人
(子ども虐待防止センター理事長、「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク共同代表)
都教組、東京地評などが参加する「子どもを貧困と格差から守る連絡会議」は9月15日に、子どもの虐待防止に取り組んでいる平湯真人弁護士を講師に招き、学習会を行いました。その内容を紹介します。
○誰を罰するかよりも
虐待は特殊な親や家庭の問題ではありません。虐待事件は誰を罰するかよりも、そもそもの防止が大事で、この立場で子ども虐待防止センターの活動を行っています。
児童相談所に情報が寄せられても、民法の親権条項で取り組みが制約されてきました。最近、民法の改正があり、児童虐待を防ぐため親権の一時停止ができるようになりましたが、親の懲戒権は制限付きで残りました。
○児童虐待をめぐる状況
平成12年に児童虐待防止法ができ、児童相談所への市民からの通告が奨励され、立ち入り調査が認められるようになりました。子どもを虐待から守る官民の取り組みの中で、通告件数は急増し年間5万余にのぼり、児童虐待による死亡は49人(47事例)と報告(平成21年度)されています。そのうちゼロ歳児が20人(40.8%)と一番多く、0~5歳児が約9割(43人)を占めています。
○虐待の背景は
貧困など社会的環境の背景についての把握が弱かったのではないでしょうか。ゼロ歳児が多いということは、生まれた時から拒否されていたと言えます。虐待が行われた家庭の状況(資料)を見ると、経済的貧困と孤立が大きな要因として絡んでいることが明らかです。虐待を防止するためには、貧困と社会的孤立を重視する必要があります。
○背景と虐待行為を繋ぐもの
しかし、経済的背景があったとしても、なぜ虐待行動をやってしまうのか、その理由はわかりにくいのが実態です。昔、家庭は生産・消費の場で、働かないことに対する体罰がありました。家庭の役割が変化しましたが、今は裕福でも将来の貧困不安を解消するために、子どもの高学歴をのぞみ、勉強を強要するケースも増えています。しつけが動機であったとしても、子どもが言うことを聞かないからと、親の支配欲求と絡んで体罰がエスカレートする傾向があります。
○学校と地域の役割~監視でなく家庭支援を
都の児童相談所のほかに、区市町村などの自治体で、子ども家庭支援センターが設置されています。地域では、虐待の怪我を探すような監視ではなく、困っている家庭の支援が求められています。
そして、「学校に福祉の発想を」の期待が高まっています。「個人情報の保護」があるから、家庭のことに口を出してはいけない、との誤解が若い先生を中心に広まっています。これでは学校の役割が先細ってしまします。今度の震災で、父子家庭だった子どもが津波で父親を亡くし、校長が、離婚した母親を探し出し、ようやく子どもと繋げることができたケースを聞きました。
先生の研修会の参加が少ないのが残念です。都教委「虐待防止のパンフレット」を作成しましたが、できれば時間をかけて研修してほしい。何よりも大事なことは、知識よりも感性の問題、顔を腫らした子どもに何が起きているか推察できる「感性」を先生に磨いてもらいたいと、願っています。
虐待が行われた家庭の状況
家庭の状況 合わせて見られる他の状況上位3つ
状況 件数 割合(%) ① ② ③
ひとり親家庭 460 31.8 経済的困難 孤立 就労の不安定
経済的困難 446 30.8 ひとり親家庭 孤立 就労の不安定
孤 立 341 23.6 経済的困難 ひとり親家庭 就労の不安定
夫婦間不和 295 20.4 経済的困難 孤立 育児疲れ
育児疲れ 261 18.0 経済的困難 ひとり親家庭 孤立
(文責;編集部)
2011年11月3日木曜日
「混ぜる」ことに可能性 松本哉さんが講演
東京革新懇は9月10日、世話人会・代表者会議を開催しました。その記念講演として、インターネットで原発ゼロのデモを成功させたことで有名な松本哉氏が『どう共同を広げるか、私の経験』と題して講演しました。
高円寺で、シャッター通の店舗を安く借りて、古物商「素人の乱」を6~7年前からやっている。
原発の爆発が起こり、「この世の終わりか」ただ事ではないと思ったのに、事故が沈静化しないうちから、政府・マスコミがうやむやにしようとしていることにヤバイと感じた。そこで仲間10人と居酒屋で話し合い、ネット上で4月10日のデモを呼びかけた。反響が大きく、2~3千人の予想を上回る1万5千人が高円寺に集まった。「事前登録は必要?」「火炎瓶は?」などの問い合わせもあり、9割はデモ初参加と思われる。その後も、渋谷、新宿、東電前とデモを続けている。
若者たちのデモの印象は「ハチマキ、ゼッケン、シュプレヒコール」、まじめで大きな団体の言うことを聞くのではと感じている。若者の政治意識が低いのではなく、表現の場がないだけ。気安く参加できて、文句(要求)が言えるように、デモのやり方は、音楽、パフォーマンスなどいろんな形式を工夫している。毎回、何があるのか、何が起きるのか、参加者が楽しくワクワクするように考えている。こんなものでしょうという「予定調和」ではなく、いつもと違う、こんなことができたと思える行動を心がけている。
このようなことができるのは、普段から、野外イベントなどの経験があるからで、インターネットで宣伝しただけで、大勢が集まったわけではない。日常的・直接的なコミュニティが大事で、商売や街づくりでのつながりの人脈が役立っている。いろんなジャンルの人が「混ぜる」ことで新たな可能性が生まれる。原発問題でも、敵は強大で、財・政・官・学など予定調和の塊である。この構造を破壊するには正しい(言動)だけではなく、強力なネットワークが必要である。力のある人、意識の高い人だけではない「ゴジャマゼ感」が大切で、よくわからなくても集まる、集まるうちにわかる。腐りきった世の中を変えるために、敵が「もう参りました」というまで頑張りたい。(文責、編集部)
高円寺で、シャッター通の店舗を安く借りて、古物商「素人の乱」を6~7年前からやっている。
原発の爆発が起こり、「この世の終わりか」ただ事ではないと思ったのに、事故が沈静化しないうちから、政府・マスコミがうやむやにしようとしていることにヤバイと感じた。そこで仲間10人と居酒屋で話し合い、ネット上で4月10日のデモを呼びかけた。反響が大きく、2~3千人の予想を上回る1万5千人が高円寺に集まった。「事前登録は必要?」「火炎瓶は?」などの問い合わせもあり、9割はデモ初参加と思われる。その後も、渋谷、新宿、東電前とデモを続けている。
若者たちのデモの印象は「ハチマキ、ゼッケン、シュプレヒコール」、まじめで大きな団体の言うことを聞くのではと感じている。若者の政治意識が低いのではなく、表現の場がないだけ。気安く参加できて、文句(要求)が言えるように、デモのやり方は、音楽、パフォーマンスなどいろんな形式を工夫している。毎回、何があるのか、何が起きるのか、参加者が楽しくワクワクするように考えている。こんなものでしょうという「予定調和」ではなく、いつもと違う、こんなことができたと思える行動を心がけている。
このようなことができるのは、普段から、野外イベントなどの経験があるからで、インターネットで宣伝しただけで、大勢が集まったわけではない。日常的・直接的なコミュニティが大事で、商売や街づくりでのつながりの人脈が役立っている。いろんなジャンルの人が「混ぜる」ことで新たな可能性が生まれる。原発問題でも、敵は強大で、財・政・官・学など予定調和の塊である。この構造を破壊するには正しい(言動)だけではなく、強力なネットワークが必要である。力のある人、意識の高い人だけではない「ゴジャマゼ感」が大切で、よくわからなくても集まる、集まるうちにわかる。腐りきった世の中を変えるために、敵が「もう参りました」というまで頑張りたい。(文責、編集部)
登録:
投稿 (Atom)